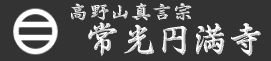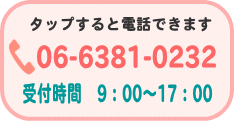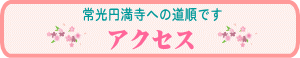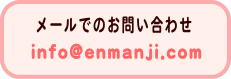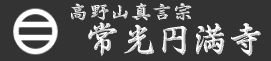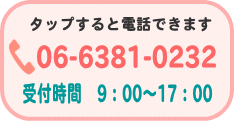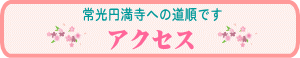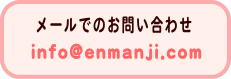七五三とは、一般的には11月15日に、3歳、5歳、7歳の子どもの無事な発育を喜び、より一層の成長を願って、神社や寺院で行う儀礼です。現代に比べて医療の発達が未熟で衛生面もよくなかった昔は、子どもの死亡率がとても高く、子どもが無事に育つことは大きな喜びであり、親として健やかな成長を願わずにはいられないものでした。それゆえ、3歳、5歳、7歳の節目に成長を神様に感謝し、お祝いをしたことが七五三の由来とされており、やがて江戸時代に現在の七五三の原型として武家や商人の間に広まったといわれています。
以下ではそれぞれのお祝いについて説明いたします。
|
3歳の男女
【髪置きの儀(かみおきのぎ)】 |
平安時代では、生まれてきたお子さまは男女ともに頭髪を剃り、3歳頃までは丸坊主で育てるという風習があったそうです。これは頭を清潔に保つことで病気の予防になり、のちに健康な髪が生えてくると信じられていたためです。
髪置きとは3歳になった11月15日頭髪を剃ることをやめて伸ばしはじめる儀式で、髪立,櫛置などとも云われます。子どもの健やかな成長や長生きを願い行われていた儀式です。
|
5歳の男の子
【袴着の儀(はかまぎのぎ)】 |
平安時代には5〜7歳の頃に、当時の正装である袴を初めて身に付ける「袴着の儀」を執り行いました。この儀式を経て男の子は少年の仲間入りをし、羽織袴を身に付けたとされています。当初は男女ともに行っていた儀式でしたが、江戸時代に男の子のみの儀式に変わりました。
儀式は天下取りの意味を持つ碁盤の上に立って吉方に向き袴をはきます。縁起がいいとされる左足から袴を履くのが良いとされています。男児から立派な少年として社会の仲間入りを果たす大事なイベントです。
また、冠をかぶって四方の神を拝んだともいわれており、これは四方の敵に勝つという願いが込められています。
|
7歳の女の子
【帯解の儀(おびとけのぎ)】 |
鎌倉時代、着物を着る際に使っていた付け紐をとり、帯を初めて締める成長の儀式が執り行われていました。これが室町時代に「帯解の儀」として制定され、当初は男女ともに9歳で行われていたとされています。
「帯解の儀」は別名「紐落し」「四つ身祝い」などと呼ばれますが、江戸時代に男児は5歳で「袴着の儀」を、女児は7歳で「帯解の儀」を行う形に変わり、この帯解を経て大人の女性へ歩み始めると云われていました。
七五三のお参りを通じてお子さまの成長を改めて感じていただき、心身ともに健康に成長されることを願っております |